自然現象との調和を図りつつ人々が暮らしやすい生活環境、社会基盤を作るための技術を学び、自然現象を理解し、社会基盤施設を計画、設計、施工、維持管理し、それが人間や生態系に及ぼす影響の評価・分析ができる人財の育成を目指しています。
本学科では、安全安心な社会を支える、社会基盤施設の整備・維持管理を担う「社会基盤系」と持続可能な技術とデジタルツインを担う「水環境・防災系」、快適で多様な活動が生まれる公共空間を市民とともに計画・創造する「計画系」の3つの系を設置しています。
振動実験装置での巨大地震体験や、隅田川周辺の水辺空間の船上からの見学などを通じて、都市環境学の全体像を理解するとともに、それを学ぶ意義、目的を明確にします。

都市の自然環境の軸となる河川・水辺を対象とし、水辺の生物と地形・水流等の基盤となる自然との相互関係及び人間の営みとの関連などを調査することにより、生態学的な知見に基づく自然環境の基本的な見方を習得します。

地域に根ざすコミュニティの「ありたい姿」を実現する仕組みと場づくりをテーマに、基礎的な社会調査および設計を実践し、プランナーとしてデザインを提案する能力を養います。

都市インフラ整備、環境管理、災害対策などについて、海外で活躍されている事例紹介も踏まえ、国際的視点で探求するとともに、海外で活躍できる人材養成を目標とします。


社会を支えるインフラの地面の下には、地上部分の重さを支える「基礎構造」があります。令和6年能登半島地震では基礎構造が耐震補強されていないビルが倒壊しました。また、地下トンネルや下水道管のような「地下構造」も重要なインフラです。当研究室では、水平2方向振動台を用いた模型実験を中心に、このような基礎構造・地下構造の設計法・施工法・維持管理技術に関する研究開発を通じて、良質なインフラ整備に貢献することを目指しています。

私たちの研究室では、津波や高潮などによる沿岸災害に強い社会の実現を目指しています。数値シミュレーションやAI、VR/ARを活用したデジタルツインの構築に取り組むとともに、マングローブなどの自然環境を活かした沿岸域の防災・減災のあり方を探究します。実験・数値解析・社会調査を組み合わせ、最先端技術を駆使し、現実世界の課題解決に資する実践的な研究に挑戦し、持続可能でレジリエントな沿岸地域の未来の創造に貢献します。
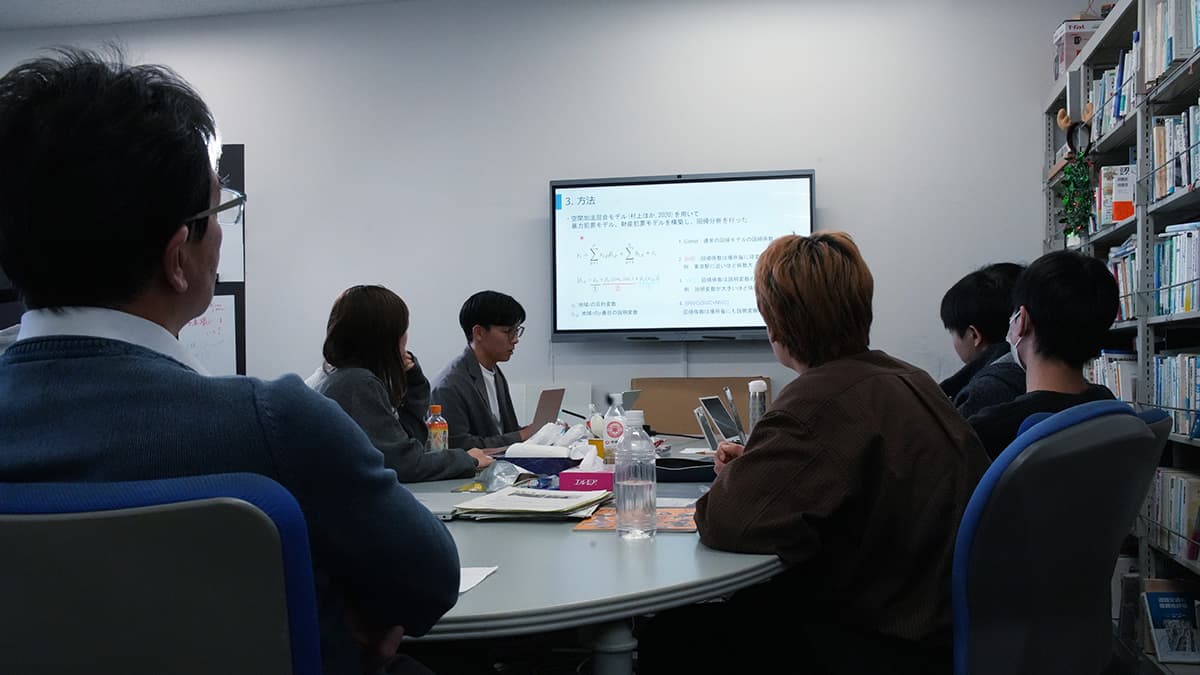
気候変動や頻発する災害、そしてAIや自動運転といった進化する技術の中で、私たちはどのように行動しているのか.またどのようなインフラや制度を整備すれば、効率と公平を両立させた持続可能な都市を築くことができるのか.交通や土地利用をテーマに、地域の特性や市民のニーズを深く理解し、空間統計や計量分析を駆使して、市民・企業・行政の意思決定を支援する研究を行っています。









国土交通省(総合職)
東京都庁
鹿島建設株式会社
大成建設株式会社
株式会社大林組
清水建設株式会社
東日本旅客鉄道株式会社
東京地下鉄株式会社
東日本高速道路株式会社
日本工営株式会社
東京電力ホールディングス株式会社